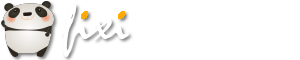2018-05-18(金)第5回
最終更新: (更新者 鈴木 靖 )
1.「歴史」から何を学ぶか?
前回の第三章のp.56では白村江の戦いについて学びました。輪読図書は日韓交流の歴史に主眼を置いているため、あまり詳しくは説明されていませんでしたが、この戦いは日本の古代史上最大の対外戦争であり、その後の日本の外交政策にも大きな影響を与えました。では、白村江の戦いからは何を学ぶことができるのでしょうか。始めにビデオを見た後、みんなで話し合いましょう。
【問題】白村江の戦いについて、高校までの歴史でどのように学んだかを振り返るとともに、これをアジアからの視点で見たとき、どのようなことが学べるかを考えてみよう。
| 豊島宏「歴史教育論攷Ⅲ 国際化時代に対応した歴史教育の在り方について」(松山大学論集第18巻第1号2006年4月) |
2.輪読発表(担当:三木・清水(岸山))
第4章 10~12世紀の東北アジア国際秩序と日本・高麗
1.東北アジア世界の再構成(太田・齊藤(中山))
2.10~12世紀の日本・高麗の関係(太田・齊藤(中山))
3.グループワーク
894年に遣唐使の派遣を中止して以降、日本は独自の民族文化を育む国風文化の時代を迎えました。その中でとくに重要な役割を果たしたのが「仮名」の誕生と普及ですが、こうした民族文字が民族のアイデンティティーや文化の発展に果たした役割について、アジア全体の視点から考えてみましょう。(→雑誌取材のため第7回に変更)