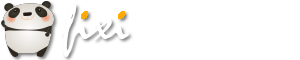2018-05-25(金)第6回: リビジョン
1.「征服王朝」の時代とは?
唐代以降、中国北方の遊牧民や狩猟農耕民たちは、民族文字の制定に象徴されるように強い民族的アイデンティティーを持つようになり、やがて遼、金、元、清という強大な王朝を建てて、漢民族を中心とする従来の国際秩序に対抗し、東アジアさらにはユーラシア大陸全土に新たな国際秩序を築いていきます。こうした新たな王朝をウィットフォーゲル(Karl August Wittfogel、1896-1988)は「征服王朝(Conquest Dynasty)と呼んでいます。こうした新たな国際情勢の中で、日本はアジアの国々とどのような関係を持つことになったのでしょうか。
【問題】1279年、南宋の滅亡により、漢民族王朝は滅亡し、中国はモンゴル帝国の支配下に入ります。こうした国際情勢の変化を当時の日本人はどのように受けとめたのでしょうか?また、それは日本のその後の外交政策にどのような影響を与えたのでしょうか?高校までに学んだ知識を振り返りながら、話し合いましょう。
2.輪読発表(担当:三木・清水(岸山))
第5章 モンゴル帝国の成立と日本・高麗
1.モンゴルの侵略と高麗・日本(発表 川井・宮本・長谷川(布施))
2.14世紀後半の東北アジア情勢と倭寇(発表 川井・宮本・長谷川(布施))
3.グループワーク
ユーラシア大陸に巨大な世界帝国を建国したモンゴル。そのモンゴルに日本は1274年(文永の役)と1281年(弘安の役)の2回、遠征を受けます。第3回目も準備されていたというモンゴルの遠征に、日本はなぜ勝利することができたのでしょうか?アジア全体の視点から考えてみましょう。
4.「渡来僧」の世紀
モンゴル帝国の拡大により、東アジアにも緊張が高まる一方で、1240年から約一世紀の間、日本と大陸との間では禅僧や貿易商人を中心とする民間交流が全盛期を迎えます。村井章介氏が「渡来僧の世紀」と呼ぶ時代です。そこでは、どのような交流が行われていたのでしょうか。
| 村井章介「国際社会としての中世禅林」(吉田光男編『アジ理解講座④日韓中の交流』山川出版社、2014年) |
履歴
2018-05-25(金)第6回
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-25(金)第6回
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-25(金)第6回
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-25(金)第6回
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-25(金)第6回
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-25(金)第6回
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-25(金)第6回
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-25(金)第6回
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )