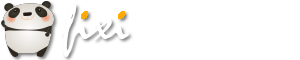2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言: リビジョン
2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
08:45 ホテルを出発
09:02 衣笠校前から204号に乗り、丸太町御前通りで202号に乗り換え、新熊野へ
10:00 今熊野神社に到着
応安7年(1374)、観阿弥は当時12歳だった世阿弥とともに、足利将軍義満の臨席の下、「今熊野」で大和猿楽の公演を行いました。これがきっかけとなり、観阿弥・世阿弥らの大和猿楽は将軍家の庇護を受けるようになります。この「今熊野」とは今熊野神社を指すと考えられており、このためこの地は「能楽発祥の地」とされています。
観阿(観阿弥)、今熊野の能の時、申楽(猿楽)ということをは、将軍家(足利義満)、御覧じはじめらるるなり。世子(世阿弥)、十二の年なり。(観世元能著『申楽談義』)
今熊野神社の鳥居に向かって左側には、後白河上皇お手植えと伝えられる巨大な樟が立っています。
鳥居の右側には今熊野猿楽復興委員会が1980年に建立した石碑群が並んでいます。石碑の絵がアニメ風なのがいかにも現代的でした。
副碑には林屋辰三郎が起草した碑文が刻まれています。
王朝の昔から神事や後宴の法楽に演ぜられた猿楽は、大和結崎座の大夫観阿弥とその子世阿弥によって今日伝統芸術として親しまれる能にまで仕上げられた。その端緒となった時は今から六百余年前の応安七年、場所はここ今熊野の社頭であった。古く八百二十年前永歴元年、後白河上皇が御願をもって紀伊熊野の森嚴なたたずまいを移されたこの地で猿楽能を見物した青年将軍足利義満は、当時十二歳の世阿弥の舞容に感銘した。そして世阿弥を通して能の大成を後援し、ついに幕府の式楽として採用したのである。現代の能の隆盛につけてもその日のあでやかな世阿弥の風姿を知る老樟の下に往時を追懐し、今熊野猿楽の復興を志ざす人々が一碑を建立してこの史実を記念することになった。ここに請われるまま碑銘の文字を世阿弥自筆本花鏡のなかゝら撰ぶとともに、その由来を録して社頭の繁栄と能の発展を併せ祈願するしだいである。昭和五十五年庚申十月十六日文学博士 林屋辰三郎
11:48 烏丸六条到着
12:09 烏丸六条から26号バスに乗り、12:23 壬生寺通りに到着。パン屋で昼食を購入し、壬生寺へ
12:30 壬生寺に到着。壬生狂言の行列は昨日ほど多くなく、予定通り12:30に開場
13:00 壬生狂言開始。途中から雨が降り出したため、前列の方は観客が少なかった。
【曲目】
①炮烙割
②花折
③道成寺
④節分
⑤熊坂
履歴
2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2018-05-02(水)壬生狂言・千本ゑんま堂大念佛狂言
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )