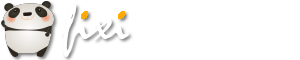2.構成表(第二稿): リビジョン
|
Seq |
映像 |
音声 |
効果音・BGM |
ナレーション |
修正案 |
|
オープニング |
国連総会で可決した時 |
|
|
2017年7月7日国連総会で核兵器禁止条約が122か国・地域の賛成多数により採択された。しかし、核全保有国は不参加、アメリカの核の傘の下にあるカナダやドイツなどNATO加盟国や日本、オーストラリア、韓国なども不参加となった。 |
|
|
① 原爆投下 |
|
|
① 1945年8月、アジア太平洋戦争の末期、広島・長崎に原子爆弾が投下されました。人類に対して初めて核兵器が使用された被害国として日本は世界に知られることになります。 ② 広島平和記念公園。毎年、原爆による死没者を弔い、世界の平和を祈る「平和記念式典」が開かれるこの公園には、原爆ドームや平和記念資料館など、原爆の悲惨さを伝える建物が並んでいます。 ③ その近くに、訪れる人もほとんどいないもう一つの慰霊碑があります。韓国人原爆犠牲者慰霊碑です。
|
|
|
|
② 原爆ドーム(式典) ③ 韓国人原爆犠牲者慰霊碑 |
|||||
|
ニュース |
|
|
1910年、韓国併合条約により、日本は朝鮮半島をその支配下に置きます。急速な近代化政策が推し進められる中、土地調査事業で生活基盤を失った人々や、労働力不足を補うために徴用された人々が、日本本土に渡ります。 1944年に内務省警保局が行った調査によれば、当時広島や長崎に暮らしていた朝鮮半島の出身者はあわせて14万人。原爆投下により、このうちの7万人が被爆したといいます。広島・長崎の被爆者総数は約69万人。被爆者の10人に1人が朝鮮半島の出身者だったのです。
|
|
|
|
広島記念公園の日本国旗
国会 |
|
|
1950年代に入り、日本国内では被爆者への医療支援が始まります。しかし、朝鮮半島にもどった約2万3千人の被爆者には支援の手が差し伸べられることはありませんでした。「同じ被爆者なのになぜ?」韓国の被爆者たちは原爆の後遺症に苦しみながらも、平等な支援を求めて立ち上がります。 いまも韓国に生きる被爆者たち。「韓国のヒロシマ」と呼ばれる陝川(ハプチョン)を訪ね、その73年の歩みを振り返ります。
|
|
|
|
|
タイトル「韓国のヒロシマ・ハプチョンからの想い〜日韓間で揺れた在韓被爆者〜」 |
|
|
|
|
|
|
① 飛行機 ② 大邱空港の外観 ③ バスからの風景→ハプチョンの風景 ④ 原爆被害者福祉会館 ⑤ 慰霊閣の外観
|
|
|
① 韓国に暮らす被爆者たちは、戦後どのように生きてきたのでしょうか。その声を聞くため、私たちは今年10月韓国に向かいました。 ② 韓国第三の都市・大邱(テグ)。 ③ 向かう先は、ここからバスで1時間半ほどの場所にある「韓国のヒロシマ」と呼ばれる陝川です。 私たちはバスを降りて歩いて10分ほどの原爆被害者福祉会館へ向かいました。 ここは在韓被爆者が最も多く住んでいる地域で、韓国のヒロシマとも呼ばれています。 ④ 現在、原爆被害者福祉会館が設立され、当時の被爆者を含む101人が生活をしています。 ⑤ 会館の裏には、陝川出身の原爆犠牲者が眠る慰霊閣があります。私たちは実際に4人の被爆者のお話を伺うことが出来ました。
|
|
|
|
|
|
|
なぜ広島に渡ったきっかけ② イルジョさんが広島に渡ったきっかけをこう語ってくれました。
|
|
|
|
音声なしで映像のみ |
|
|
(当時の広島市には三菱重工業の造船所などがあり、日本の主要軍事都市だったことから徴用で日本に渡る朝鮮人もいました。) →インタビュー
|
|
|
|
|
|
|
(怪我のエピソード アンウォルソンさん) 『あの時頭巾を被っていれば自分の顔に傷は残らなかった。』(原爆の悲惨さ)
|
|
|
|
アンさんのインタビュー映像 |
|
|
原爆投下からわずか9日後の8月15日、日本の「ポツダム宣言」受諾による無条件降伏で、植民地支配から解放されました。しかしそれと同時に、在韓被爆者にとっての苦難の日々が始まりました。
|
|
|
|
アンさんの帰国エピソード |
|
|
原爆から生き延びた朝鮮人約3万人のうち約2万3千人が、被爆した体で独立を果たした祖国へ帰っていきました。
|
|
|
|
イルジョさんのインタビュー映像 |
|
|
イルジョさんの説明 (しかし祖国にたどり着いたところで治療費を払う余裕などありません。またたとえ病院に行くことができたとしても、原爆症とその治療法について知る医者がいない状況でした。)
|
|
|
|
|
|
|
さらにその5年後に朝鮮戦争が始まり、社会が混乱する中、在韓被爆者の存在は世間から見捨てられていくのです。
|
|
|
|
国会 → シム・ジンテさんが資料館で怒りの部分 |
|
|
終戦から20年後の1965年、韓国との国交正常化が実現します。その際に結ばれた「日韓請求権協定」によって「(日韓両)国及びその国民の間の請求権に関する問題」は「完全かつ最終的に解決されたこと」が確認されました。 しかし、この交渉の中で、韓国の被爆者への補償が議論されることはありませんでした。 (シム・ジンテさんの説明) 1967年、被爆者たちは韓国原爆被害者協会を起ち上げます。
|
|
|
|
被爆者健康手帳 (映像or写真) |
|
|
日本では1957年に「原爆医療法」が制定されました。広島・長崎の原爆被害者であることが認定されれば、この「被爆者健康手帳」が交付され、国の負担で健康診断と原爆症の治療が受けられるようになりました。 韓国原爆被害者協会は日本政府に日本人被爆者と同等の援助を与えるよう求めます。
|
|
|
|
シム・ジンテさんの怒りの部分 |
|
|
1968年、日本ではさらに被爆者の生活を支援するための手当支給を定めた「原爆特別措置法」が制定されます。 しかし、この二つの法律の適用については、居住の本拠地が日本国内であることが前提とされていたため、韓国の被爆者が「被爆者手帳」を受け、医療費の支援や生活費の手当を受けることはできませんでした。
|
|
|
|
|
|
|
そうした中1974年、在韓被爆者が初めて手帳を取得出来ました。日本人被爆者と同等の援助を受ける権利が与えられたと歓喜に沸きました。ところが日本政府は402号通達です。402号通達とは、在韓被爆者が日本で手帳を取得しても、韓国に帰国すると医療費と被爆者手当の支給も打ち切られてしまうというものです。 |
|
|
|
|
|
|
1979年、在韓被爆者も日本に行けば手帳を手に入れられるようになりました。しかし原爆被害者だと認定されるには証言者を探さなければならず、手帳取得が依然として難しいのが現実でした。
|
|
|
|
|
|
|
(キムイルジョさんが証人探してあげたエピソード)
|
|
|
|
陜川原爆被害者福祉会館の外観や歩いている所 |
|
|
1990年5月24日に行われた日韓首脳会談で、日本政府は在韓被爆者に対し医療支援金40億円を拠出することを明らかにしました。私たちが訪れた陜川原爆被害者福祉会館は、この40億円の支援金で建てられたものです。40億円で韓国内での治療費が支給されるようにはなったものの、日本ほど適切で満足のいく治療は依然として受けられないことから渡日治療を望む人が後を絶ちませんでした。しかし多くの韓国人被爆者とっては、40億円は臨んだ金額には及びませんでした。 |
|
|
|
スヨンさんのケガ |
|
|
韓国人被爆者は原爆の後遺症と貧困という二重の苦しみを負わなければならなかったのです。
|
|
|
|
|
|
|
2003年に402号通達廃止、2008年韓国で手帳交付が可能に、2010年原爆症認定の「来日要件」撤廃、そして2015年には最高裁判所の判決により在外被爆者にも日本国内の被爆者と同等の医療費の全額支給が認められます。
|
|
|
|
原爆資料館の外観
資料館の中の写真
皆がシムさんの話を聞いている姿
(由紀夫のニュース記事) |
|
|
2017年、シムジンテさんは念願の夢であった韓国初の原爆資料館をオープンさせました。 原爆資料館には陜川在住被爆者の証言や被爆者の持ち物、在韓被爆者の歴史をたどった年表が展示されています。資料館の中央にある4段に重なる明かりは、原爆が落とされたときにできたキノコ雲を表しているそうです。
(鳩山由紀夫元首相も来館)
|
|
|
|
|
|
|
「唯一の被爆国、日本」という認識は在韓被爆者の存在を見落とした認識でしょう。私たちは日本人が受けた被害については歴史として学びましたが、同じときに同じ場所で同じような被害を受けた人が他にもいるという事実は広くは知られていません。韓国にも、今なお原爆被害によって苦しんでいる人がいることを私たちは知る必要があります。今回インタビューした方々は、当時、日本で生まれ日本語を話し、日本で生活し、日本で教育を受けていました。彼らは確かに「日本人」として生きていました。
|
|
|
|
|
|
|
(映像:シムさんのインタビュー映像最後)
植民地統治の時代、在韓被爆者の方が日本人として生きてきた状況を考えたときに、彼らが日本に補償を求める思い(弱い)を理解することができるのではないでしょうか。 国籍や民族という枠組みを超えて、1人の人間として相手に寄り添う。それは、これから国際社会の中で生きる私たちにとって重要な考え方ではないでしょうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
履歴
2.構成表(第二稿)
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )2.構成表(第二稿)
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )