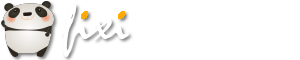日本の年号のはじまりは645年?701年?: リビジョン
645年、乙巳の変のあと、皇極天皇の禅譲を受け、弟の軽皇子が即位します。孝徳天皇です。
孝徳天皇は、中国から帰国した僧旻と高向玄理を国博士に迎え、制度改革を行います。僧旻と高向玄理は遣隋使とともに中国に渡った留学生で、留学期間は僧旻23年、高向玄理32年。中国の制度を熟知した二人のアドバイスを得て、日本に中国の新たな制度が導入されました。
その一つに年号があります。『日本書紀』巻第二十五孝徳天皇紀を見ると、
天豊財重日足姬天皇(あめとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと=皇極天皇)四年を改め、大化元年と為す。
とあり、645年、新たに「大化」という年号が使われるようになったことがわかります。
では、日本の年号はこの年に始まると考えていいのでしょうか。
実は、このあと年号は使われたり、使われなかったりといった時代が続きました。このため北畠親房などは『神皇正統記』の中で、
(文武天皇の)御時、唐国の礼をうつして、宮室のつくり、文武官の衣服の色までもさだめられき。又即位五年辛丑(701年)より、はじめて年号あり。大宝と云ふ。これよりさきに、孝徳(天皇)の御代に大化、白雉、天智(天皇)の御時白鳳、天武(天皇)の御代に朱雀、朱鳥なんど云ふ号ありしかど、大宝より後にぞたえぬことにはなりぬる。よりて大宝を年号のはじめとするなり。
と、日本の年号は「大宝」に始まるとしています。
北畠親房のいうとおり、年号は使ったり使わなかったりしては困りますから、制度として定める必要があります。「大宝」以降、今日にいたるまで、年号が中断されることなく続いているのは、このとき定められた『大宝律令』に年号使用に関する規程が設けられたからです。
『大宝律令』そのものは伝わっていませんが、これを改定した『養老律令』の注釈書である『令義解』巻六に、
凡そ公文のまさに年を記すべきは、皆年号を用いる。
とあります。
大宝年間に年号の使用が法的根拠をもったことにより、日本の年号が正式に始まったといえるでしょう。
 |
『日本書紀』巻第二十五孝徳天皇紀 |
 |
北畠親房『神皇正統記』(岩波文庫 1934 年) |
 |
清原夏野『令義解』巻第六儀制令第十八(国立国会図書館デジタルコレクション) |
履歴
日本の年号のはじまりは645年?701年?
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )日本の年号のはじまりは645年?701年?
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )日本の年号のはじまりは645年?701年?
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )