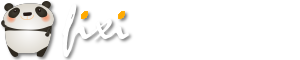第13回 北宋時代(下)三国志の誕生: リビジョン
最終更新: (更新者 鈴木 靖 )
第12回 北宋時代(下)三国志の誕生
日本で藤原氏一門が権勢を極めていた平安時代、中国では武人の台頭によって貴族の時代は終わり、庶民の時代が始まっていました(唐宋変革期)。
文学の主体も貴族から庶民に代わり、詞の隆盛や本格的な演劇の誕生とともに、史書を素材とする「説古話」と呼ばれる歴史講釈が人気を博していました。
日本の琵琶法師が語った『平家物語』と同様、仏教思想の影響を強く受けた「説古話」は、出版業の発展とあいまって、仏教の絵解き講釈を模した挿絵入りの通俗読み物として出版されました。その一つが元代に刊行された『全相平話三国志』です。
明代になると、モンゴルの支配を脱した漢民族は、外来の仏教思想を排して、民族の伝統思想である儒教を基にこの物語の改編を行います。こうして誕生したのが、中国の俗文学を代表する『三国志演義』です。
最終回の今回は、中国文化の集大成ともいうべき『三国志演義』の誕生について考えます。
| 授業用スライド | |
| 三国志演義梗概(上)(中国ドラマ『新三国志』第1集より) | |
| 董卓暗殺(日本語版)(中国ドラマ『新三国志』第1・2集より) | |
| 呂伯奢一家惨殺(上)(日本語版)(中国ドラマ『新三国志』第3集より) | |
| 呂伯奢一家惨殺(下)(日本語版)(中国ドラマ『新三国志』第3集より) | |
| 北宋の都・汴京と清明上河図(NHKスペシャル『故宮』第8集より) |
履歴
第13回 北宋時代(下)三国志の誕生
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )第13回 北宋時代(下)三国志の誕生
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )第13回 北宋時代(下)三国志の誕生
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )第13回 北宋時代(下)三国志の誕生
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )第13回 北宋時代(下)三国志の誕生
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )第13回 北宋時代(下)三国志の誕生
リビジョンを作成しました: (作成者 鈴木 靖 )